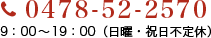今月の漢方
漢方の本領ー「瞑眩(めんげん)について」その3

それでは、前回のこの私の経験を、古人の記録に徴してみましょう。
恐れながらご登場頂くのは、江戸時代中期の京都の医家・吉益東洞(よしますとうどう 元禄15~安永2 1702~1773)先生である。先生は文字通りそれまで2千年間も途絶えていた、この「瞑眩させる漢方」を復活させた漢方医学者であり、実地に応用して驚異的な治験を上げた漢方医である。この先生の著書多数ある中、「医事或問(いじわくもん)」という書物に、この「瞑眩」の著しい症例が掲載されているので紹介させて頂きます。
この「医事或問」の原文は漢文ではなく和文ですが文語体ですので、現代文に訳しました。ただ、私の訳なので、国語的に正確でない所があるかも知れない事と、訳しにくい専門用語はそのまま使った所、また意訳した所などがありますが、大概の意味は間違ってないと思いますのでご了承頂きたいと思います。では、
「自分(吉益東洞)は、以前京都祇園町に住む伊勢屋長兵衛という人を治療した事があった。その病人は腹下しの病気であるが、どの町医者が治療しても治らないという事で、自分に診察を依頼して来た。往診してみると、心下痞鞕、水瀉嘔逆して、まさに瀕死の状態であった。自分はその家族に 『この病人の治療は、世上大いに恐れられるものである。なぜなら世間一般の漢方医が甚だ穏やかな薬方であると言う処方でも、この人に用いて病毒に的中する時は大いに瞑眩するものである。その瞑眩に恐れていては、この病気は治るものではない。』 と言ったところ、病人の家族も納得して、その薬を下さいと言った。
そこで、生姜瀉心湯(ショウキョウシャシントウ)という処方を3回分用いたところ、その日の七つ時分(午後4時頃)に、大いに吐瀉(吐き下し)して病人は気絶してしまった。これによって家中大騒動になって、医師を呼び集めて診てもらったところ、どの医師も皆 『死したり』 と言って帰ってしまった。それゆえ急にまた自分が招かれたので、行って診察したところ、色脈呼吸、皆絶えており、病家の者も病人はすでに死んだものと思っていた。しかしながら、まことに死したるように見えるけれども、その形状には(死亡と断定するには)少し疑問な点があった。その上、このように”死んだ”状態になって漸くふた時(4時間)ばかりであるので、『まずは落ち着いて様子を見て、それからいよいよ死したるか、死せざるかを判断しよう。薬は同じものを口に入れて通ればまた入れるように。』 と言って帰った。
すると、その夜七つ時分(午前4時頃)、病人は夢のさめたる如く目を開き、『一類眷属集まり居るは何事ぞ。(一族親戚が集まっているのは何事なのだ)』 と問うた。一族の者も驚いて、『今日、昼の七つ時分より只今まで呼吸色脈ともに絶えていて、医者を集めて見せたけれども、死人に薬無し、と言って皆帰ってしまうので、皆々集まっている。』 と言ったところ、病人も不思議そうに 『昼のうち、大いに吐き下ししたが、その後一向に病苦もなく、ただ寝ているように感じていた。もはや気力もついて良くなったから皆々帰ってくれ。』 と言った。しかし一族の者はいぶかしく思って、昼に見せた近所の医者に診察してもらったが、『脈も平常で何も病気が無い。』 と言って帰るので、病人もいよいよ気力を得て、『もう大丈夫だから、お帰り下い。』 と言うので、一族の者も皆帰った。そのあと、病人は『甚だ飢えたり。(とても腹が減った)』 と言って、御茶漬を3杯食べて、喜んで就寝したのだったが、翌朝には益々丈夫になり、多年の病を忘れたようであった。
この人は幼年より、よく食べ物にあたるので白粥にて養育され、40歳を越えても食べ慣れないものを食べると直ちに食あたりするので食べられなかったが、この病気が治って後は何を食べてもあたる事なく、七十までも壮健に暮らしたのであった。
この病人の場合も、最初から毒を(体のどこに病毒があるかを)見て、その毒に方をつけて(漢方処方を的中させて)治療するのみである。」 続く